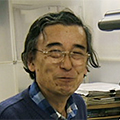今回は、いろは横丁でまちづくりを行ってきた結果である効果についてお話したいと思います。
今回は、いろは横丁でまちづくりを行ってきた結果である効果についてお話したいと思います。
まちづくりを進めていく上で重要なのは、当たり前のことですが、みんなで合意したコトを実行し、反省点を踏まえ修正し、成功を増やしつつ、どれだけの効果が得られたかということだと考えています。
 例えばイベント後の“オツカレサマデシタ”という集団的自己満足?で終わってしまい、本当の反省会や定性的(感覚)な評価や定量的(数値)な効果を測定し、チェックして、次に繋げる(面倒くさい)作業が意外や少ないようです。
例えばイベント後の“オツカレサマデシタ”という集団的自己満足?で終わってしまい、本当の反省会や定性的(感覚)な評価や定量的(数値)な効果を測定し、チェックして、次に繋げる(面倒くさい)作業が意外や少ないようです。いろは横丁では、まちづくり活動の効果をチェックするためお店の方々を対象にアンケート調査と歩行者の通行量調査を定期的に行っています。
結果としてアンケート調査では、横丁を活性化するための取り組みについて、約9割強の方々が賛同していることがわかりました。つい数年前のことを考えるとカンムリョウですね!
また、一年前と比較して、横丁を歩いている人の数は増えたか聞いたところ、「減っている」が49%と最も多く、次いで「変わらない」が37%、「増えている」、「少しだが増えているが」14%と「減少している」と考えている人が最も多い結果となったのでした。
通行量調査は、いろは横丁が面しているアーケード街(サンモール一番町)の通行量が13,352人と前年比?2.7%減、アーケード街からいろは横丁に入った人が1,408人、前年比7.8%の大幅増となったのでした。
いろは横丁全体の通行量は、前年比1.8%の微増という結果となりましたが、面しているアーケード街側などの通行量が大きく落ち込んでいることを考慮すると大健闘していたんです。
ここでおもしろいのは、アンケート調査の歩行者通行量の感覚と実際の数値に大きな乖離が見られることですね!どういうことなんでしょう フシギデス?


 続いて縁台や板塀、昭和レトロな外灯、そして井戸の洗い場の整備と少しずつ手づくり感一杯の井戸端が創られていくにしたがい、当初イメージしていたより多くの方々が井戸端に愛着を持って接していることを肌で感じることができ、この井戸端が文字通り、井戸端会議が出来る新しい溜まり場、まちなかの異空間、路地裏のフォリーとして復活することができたのでした!
続いて縁台や板塀、昭和レトロな外灯、そして井戸の洗い場の整備と少しずつ手づくり感一杯の井戸端が創られていくにしたがい、当初イメージしていたより多くの方々が井戸端に愛着を持って接していることを肌で感じることができ、この井戸端が文字通り、井戸端会議が出来る新しい溜まり場、まちなかの異空間、路地裏のフォリーとして復活することができたのでした!